かつては高級装備として知られていた車のヘッドライト、HID。ハロゲンと比べて圧倒的な明るさとファッション性の高さから、多くの車に採用されています。
約20年程前は1部の高級車や限られた車しか純正装備として存在しておらず、社外品もとても高価で工賃を含めて20万~など、そんな時代でした。
今では軽自動車でさえもHIDを選択できるようになっており、ヤフオクやAmazonではとても安価な社外HIDも販売されていて、気軽にハロゲンからHIDへ換装することができる世の中に。
そんなHIDですが今やLEDの進化で徐々にその座を奪われつつあり、種類によっては製造が禁止されてしまうようです。
H.I.Dについて
ハロゲンよりも長寿命・高効率

電極間の放電を利用しているためフィラメントがなく、白熱電球と比べて長寿命・高効率である。メタルハライドランプはテレビや映画などの演出照明分野でも、その高輝度、高効率、太陽光と色温度が近い、などの特徴をいかし、ロケーション照明の主力となっている。近年ではシールドビームやハロゲンランプに代わって自動車や鉄道車両などの前照灯に用いられるようになってきている。
Wikipediaより
自動車では主にヘッドライトとして使用されてきた。車種によってはフォグランプでも採用され、夜間の走行時にはとても役に立つ。
ハロゲンと同じようにHIDにも多様なバルブがあり、黄色がかったものから青白いものまで様々。それぞれオートバックスなどの車用品店で常備されている。
通常のハロゲンヘッドライトと比べると明るさは段違いで、かなり明るい。直視できないほど眩しい。
HIDにはバラストが必要
ハロゲンバルブは車両にポン付けで装着でき、誰でも簡単に交換が行える。しかしHIDには専用の装置が必要になり、ハロゲンからHIDにしようと思ったとき、HIDバルブだけでは意味をなさない。バラストと呼ばれる箱型の専用装置が必要になる。
近年ではHIDも進化してハロゲンバルブのカプラーから電源が供給できる仕組みが確立され、ほぼポン付けに近いインストールでセットアップが可能になっている。
このバラストの設置スペースを考えるのがちょっと面倒ではあるが、技術の進歩でどんどん薄型になり、最近ではあまり悩む必要はなくなった。
今はバラストが基本完全防水で雨に濡れても問題ない。この点でも設置の自由度が高まっている。
上記のカプラーオン方式が増えたおかげでフォグランプのHID化や、ハロゲンしか設定のなかった古い車にも簡単にHIDが装着できる。一昔前まではバッテリーから配線を回したり、色々と配線加工が必要で少し敷居が高いカスタムであった。
HIDカスタムの注意点
対向車の迷惑になる可能性がある
車のヘッドライトは対向車に配慮して、対向車が眩しくないような配光にライトの向きが調整されている。このことを一般的には光軸と呼ばれている。HID化することによって光軸のバランスが崩れてしまい、対向車を走る車のドライバーの視線へ入り込むような配光になってしまい、非常に迷惑なヘッドライトになってしまう可能性が出くる。
このため、HID化した際にはきちんと整備工場で光軸を調整してもらうことが必須だろう。
恥ずかしながら私も過去、そのような経験がある。スズキのKeiのヘッドライトをHID化したときのことだ。ヤフオクで総額5,000円もしないHIDキットを装着、明るくなったことに満足し、毎日通勤していた。
1週間程経ってからだろうか、走行していて気づいたことがある。対向車の車が度々パッシングしてくるのだ。最初のうちは気にしていなかったけど、ある日ふと思った。ひょっとして自分のヘッドライトが眩しいのではないか?と。
試しに自分でライトの光軸を最大まで下げてみた。すると一切パッシングされなくなった。やはり自分のライトが眩しかったんだなあ、と確信し、後日整備工場できちんと調整を受けた。
思えば随分遠くの道路標識まで明るく照らしているし、HIDにするとここまで明るくなるんだなあ。なんて軽く考えていたけど、多くのドライバー達に迷惑をかけながら走行していたわけだ。
安物HIDキットに要注意
グレアの問題

画像の物はバラスト一体型のHIDキット。これで7,000円程だったかと記憶している。キャデラックDTSのフォグ用に購入した物だけど、スペースの都合で取り付けできず。結局返品して通常のバラスト別対の物と交換してもらった。
こういった安物のHIDには注意するべき点がいくつかある。
まず1つ目はグレアのことだ。
HIDを装着して点灯したとき、眩しいと感じたり、乱反射しているような?と思ったことはないだろうか?まるでヘッドライト全体が光っているような…。光軸が出ていない可能性も捨てきれないけど、多くはグレアが出ていて配光が適切ではないためにそのような状況になってしまう。
これをクリアするのは難しい問題で、そもそもバルブの構造上の問題からグレアが発生することもあるし、他にはハロゲン仕様のリフレクターヘッドライトをHID化すると、発生しやすいとされる。
特にH4のHi/Low切り替え式の安物HIDはヒドイ。バルブに付いている遮光版が完全な働きをしていないことが多く、Lowの状態でも上方向へ光を照射してしまい、迷惑この上ない。これを解消するにはバルブを改造して光の漏れをなくすしかない。

ここに改造例の実例が記載されている。
リフレクターヘッドライト式車両をHID化する際は安物ではなく、信頼性のあるメーカーの物を使用するのが好ましい。高価ではあるがベロフやPIAA製など。特にベロフは日本製を謳っているので安心できるブランド。それでも正しい配光に持っていくことは難しい。
ハロゲンバルブと比べて約3倍もの光量を持つHID。もともとハロゲン仕様で設計されているヘッドライトにHIDを付けることがそもそも無理がある、という話。配光が崩れて当然と言える。
故障の問題

私も過去に様々なHIDバルブ・キットをヤフオク、Amazonで購入してきた。1つ言えることは高確率ですぐに故障する、ということ。
その中で上記画像の物は1番最悪なものだった。使用して半年でバルブが破裂したのだ。
突然片方のライトが消灯、ヘッドライトのON/OFFを繰り返すも点灯せず。これは早速壊れたか?と疑ってバルブを外してみるとバルブが破裂していた、という悲惨な状況になっていた。
バルブが破裂した原因は不明。これは初めてのことで周りにもバルブが破裂した、という経験をした人もいない。結局原因はわからずじまいで、新しく買い替えることになった。
この件で最も最悪だったことは破裂したバルブの破片がヘッドライト内に散らばり、破片がそこかしこに付着して取れなくなってしまったことだ。
バルブは点灯中相当の熱を持つので、破裂した破片もそれ相応の熱を持っていたらしく、ライトハウジング内で刺さっていた破片は「刺さっていた」というよりも、ハウジング内を溶かして「溶着していた」といった表現もできた。
こうなると破片を取り去ることは不可能に近く、泣き寝入りするしかなかった。ヘッドライトはちょっとした限定仕様のヘッドライトだったので、本当にこのときは残念でならなかった。
このように破裂したケースは稀だと思うけど、よくあるトラブルが購入してからすぐに点灯しなくなった、というのが圧倒的。1年以内に不点灯になったバルブはざらにあった。
だけどそこは安価なHIDキット。壊れたら買い替えて新品にする、ということも選択肢として挙げられるのでそこまで困ることはないかもしれない。新品でも4,000円前後あればバラストまで購入できてしまう。また付け外しの手間はかかってしまうけど。
巷に溢れかえっている安物HIDは中身は大体全て同じもので、パッケージを変えて販売されているだけ、と聞く。業者によっては販売力に差をつけるためや、同業者との競争に競り勝つために、独自に保証を設けているところもあるので、もしヤフオクなどの安物HIDを購入するなら保証付きの業者・メーカーを選んでおいた方が不点灯になっても対応してくれるので、そういった点にも留意しながら探すことをオススメする。
1部のHIDバルブが製造・輸入禁止になる
水銀に関する条約
1部の蛍光灯が2018年以降、水銀灯等が2021年以降に製造・輸出入禁止となる。条約の主な内容としては以下。
電池、化粧品や血圧計など水銀を含む9種類の製品の製造・輸出・輸入を2021年以降禁止
- 輸出の際は輸入国の事前の書面同意を義務づけ
- 歯科用水銀合金の使用を削減
- 小規模金採掘は使用を削減し可能なら廃絶
- 新規水銀鉱山の開発禁止
- 既存鉱山からの産出は発効から15年以内に禁止
- 石炭火力発電所からの水銀排出削減
- 50カ国が批准してから90日後に発効
照明に関しては
・一般照明用の高圧水銀ランプの製造・輸出・輸入を2021年以降禁止
・メタルハライドランプ・高圧ナトリウムランプは規制対象外
・紫外線ランプなど一般照明用以外の特殊用途用ランプは規制対象外
・蛍光ランプは、水銀封入量を規制(5~10mg)
と定められている。水銀条約~水銀に関する水俣条約~
HIDバルブ形式でD1、D2は水銀が使用されており、この形式は今後は製造、輸入禁止になる可能性が大いにある。D3以降のバルブは水銀フリーなので影響を受けない。
思えば街頭が少しづつLEDに変わっていってるのを感じる。他、学校の体育館や製造現場で使われている水銀灯なんかも徐々にLEDや代替え品へ交換されているらしい。
私のキャデラックDTSはD1Sなのでもしかすると直撃ですね。だけど珍しい規格なので数も出ないし、しばらくは国内の在庫で頑張ってくれるでしょうけど….。
マナー、法規にそってHID化を楽しみましょう

HIDバーナーについて
色温度が低いバルブ
光量が大きく悪天候時の視認性が良好。新車時初期に装着されているようなバーナー。特に大雨が降った日の夜など、優れた視認性を発揮。黄色味が強くなるほど視認性に優れていく。好みの問題ではあるけどドレスアップ視点、ファッション性としての観点からだとあまり….といった感じに見られがち。
色温度が高いバルブ
点灯時の「蒼白い光」が特徴的なバルブになっていく。見た目のカッコよさ、といった部分では色温度が高いバルブの方が好まれやすい。これはHIDにかかわらず、ハロゲンでも同じことが言える。
しかし色温度が低いバルブとは対照的に悪天候時の視認性はあまり良くない。そのため実用性では劣る。場合によっては車検にも通らないこともある。
ケルビン数で見るバーナーの特徴
3000K 「黄色」
雨や、霧、雪等の悪天候時に視認性が高い。雨粒に色がつきやすく、夜間の安心性が高まる。 H18年式以降の車両に前照灯として使用すると車検非対応。 以前は問題なく車検も通ったのだが、近年改正された。この部分は気を付けたい。
4000K前後 「白色」
純正HIDによく採用される色温度域。光量が最も大きく、視認性に優れているとされている。この辺りのケルビン数だとメーカーや車種によっては、若干黄色みを帯びているバーナーもある。個人的には1番故障率が少ないと感じる温度領域。
5000K前後 「純白色」
HID特有の真っ白な光を照射する。色々なメーカーから数多く販売されているので選択肢が豊富。視認性とファッション性をバランスよく兼ね備えた色温度。
6000K前後 「蒼白色」
純白光からだんだん青みがかった色になり、同時に光量が落ちる。 夜間の悪天候時で視認性が悪くなってくる。検査員の主観によって車検に落とされる場合もあり、車検を受ける際には注意が必要になってくる。若干青い色、というのが多くの若いユーザーの支持を得て、5000K辺りに次ぐ人気のあるバルブ。
8000K前後、またはそれ以上
車検非対応、公道走行不可。悪天候だともはやはハロゲンバルブのほうが明るく感じる。 ドレスアップ専用。どういうわけか様々な色が存在する。緑、ピンク、真っ青、そのどれもが見づらく「暗い」。実用性は皆無。
紹介したように対向車の妨げになるようなHIDカスタムは避けるべき。車検も通らなくってしまうので、しっかりと光軸は調整しよう。ライトを明るくしたい気持ちもわかりますが、マナーを守って楽しいカーライフを送りましょう。
ちなみに筆者オススメの色味は5~6,000ケルビン位でしょうか。見やすさで言えば純正ケルビン数の4,000前後ですが、見た目と機能性のちょうどいいトコロ、がこの辺りではないかと。車検も問題ありません。

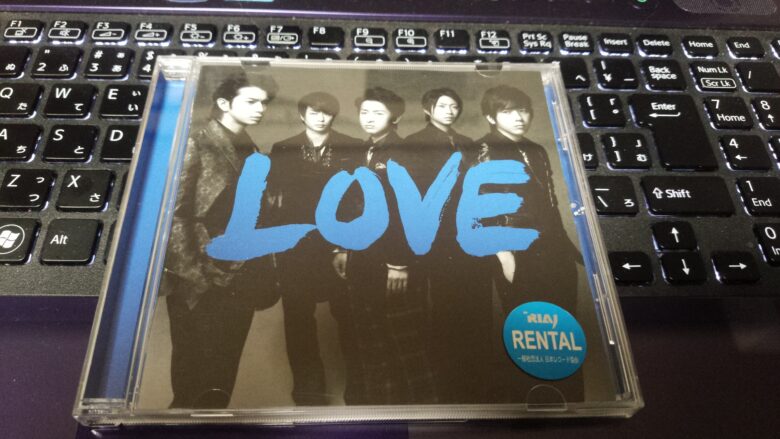

コメント